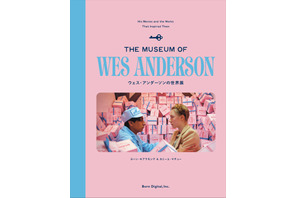『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』はウェス・アンダーソン監督の記念すべき第10作目の長編映画。日本文化へのリスペクトが詰まった前作のストップモーション・アニメーション『犬ヶ島』とは打って変わり、彼自身が夢中になった往年のフランス映画や「ザ・ニューヨーカー」誌へオマージュを捧げた映画世界が繰り広げられている。
その世界観は、ウェス作品御用達のプロダクション・デザイナーであるアダム・ストックハウゼンによれば「フランスの古い映画や写真でよく目にする、すすけた世界」とポップな色彩が調和しており、オープニングからエンドロールまで情報量が半端ない、まるで“観る雑誌”のごとき完成度。ウェス作品の常連であるティルダ・スウィントンが「(ウェス監督が)フランス語で書いたラブレター」と評するのも納得の作品となっている。
活字好きにはたまらない!?
ウェス監督が贈る“観る雑誌”

『ムーンライズ・キングダム』から『グランド・ブダペスト・ホテル』『犬ヶ島』とウェス作品に参加してきた名優ボブ・バラバンは、「10作目でもウェスの冒険心は尽きない」と特別映像の中でふり返っている。その尽きることのない冒険心は今回、20世紀フランス、架空の街にあるアメリカの新聞社「カンザス・イヴニング・サン」の支局で編集されている雑誌「フレンチ・ディスパッチ」の緻密な“誌面”に惜しみなく、もちろん遊び心も忘れずに注がれることになった。
冒頭から、活字カルチャー好きが心躍るオープニング。やがて飲み物を手にしたウェイターが縦長の建物を延々と上っていく。その行き着く先が、ビル・マーレイ演じる「フレンチ・ディスパッチ」創刊者にして編集長のアーサー・ハウイッツァー・Jr.の部屋だ。ところが、アーサーは最新号制作中に急死、その遺言に従って編集長の追悼号が最終号となってしまう。

本作は、この名物編集長のためにひと癖もふた癖もある記者たちが「フレンチ・ディスパッチ」に寄稿したアンソロジーの体裁をとり、4つの短編からなるオムニバス映画のようになっている。まずは、お馴染みオーウェン・ウィルソン演じる記者エルブサン・サゼラックが、舞台となる架空の街アンニュイ・シュール・ブラゼをその裏道まで自転車で巡り、レポートにしたためる。

続いては、ティルダ演じる美術界の表裏を知り尽くした批評家J.K.L.ベレンセンが、獄中の天才画家モーゼス・ローゼンターラーによる「確固たる名作」について執筆。ウェス組常連俳優の1人、フランシス・マクドーマンド演じる高潔なジャーナリストのルシンダ・クレメンツが、ティモシー・シャラメ演じる学生運動のリーダー、ゼフィレッリ・Bを取材した「宣誓書の改訂」を仕上げ、ジェフリー・ライト演じるローバック・ライトが警察署長お抱えの天才シェフを取材しながら、とある誘拐事件に巻き込まれる「警察署長の食事室」へと続く。街、アート、革命、グルメと、まさにフランスの象徴が詰め込まれたような構成だ。

だが、フランス生まれで本作の音楽を担当する作曲家アレクサンドル・デスプラは、本作で描かれるフランスは「監督の頭を通したイメージですから、すこし歪んでいます」と明かす。それはウェス監督の膨大な知識と記憶とイマジネーションから生まれた、あくまでも本物っぽく見える「詩的なフランス」なのだ。
超豪華キャストにワクワク!
初参加組ティモシー・シャラメらに注目

そんな「フレンチ・ディスパッチ」誌をスクリーンでめくっていくプロセスは、上に挙げた以外にもレア・セドゥやエイドリアン・ブロディ、マチュー・アマルリック、シアーシャ・ローナン、エドワード・ノートンら、何本もの映画が作れるビッグネームや名だたる賞に輝く豪華俳優たちが絶え間なく登場することもあって終始ワクワク。その分、一度見ただけでは全貌を語りきることができないほどの情報が各シーンに凝縮されている。
だからこそ、お気に入りの雑誌のように何度でも確かめたくなる妙味があり、「フレンチ・ディスパッチ」の表紙イラストを手がけているデザイナー、ジャヴィ・アズナレツによる“バックナンバー”もじっくりと眺めてみたい衝動に駆られる。エンドロールまで見逃し厳禁だ。

また、ウェス組初参加ながら、この世界観に見事に馴染んでいるベニチオ・デル・トロが演じた天才画家は、ジャン・ルノワール監督『素晴らしき放浪者』(1932)で怪優ミシェル・シモンが演じた“放浪者”がヒントになったという。ジェフリーが巻き込まれる誘拐事件や銃撃戦はフィルム・ノワールの雰囲気もありながら、アニメーションも盛り込まれるなど、フランス映画史を紐解ける一面もある。
とりわけ、1968年の五月革命を彷彿とさせる「宣誓書の改訂」に登場した、珍しくヒゲを伸ばしたティモシーの姿や『パピチャ 未来へのランウェイ』のリナ・クードリが演じるヘルメットを被ったショートカットの会計係ジュリエット、さらに白いシーツに包まる“2人”などは、ヌーヴェルヴァーグの旗手ゴダールやトリュフォーの映画の登場人物のよう。どこか懐かしくもフレッシュな魅力があり、思わず“付箋を貼りたくなる”1ページとなっている。

『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』は全国にて公開中。