観客のことを考えての作品づくり「手を抜かない」
――「自分の表現を追求していくこと」と「有名になる」ことは相反する部分があり両立が難しいこともあるのかなと思うのですが、どんどんキャリアを積まれて注目度も年々高まっているおふたりはこの両立をどう捉えてらっしゃるのでしょうか。
藤井:20代の頃は「原作ものはダサい、オリジナルで自分が表現したいことをやるんだ」って尖っていた時期はあったと思うんですが、今はそれが洗練されたと言うか、売れるものが100%正しい訳じゃないってことは正直みんながわかっていることなんですが、でも自分がやりたいことだけが100%正しいかと言うとそうでもなくて、その全ては観る方が決めることであって。
自分たちはちゃんと観客のことを考えて作品にどう向き合ってどう作るのかってことに誠実であれば、それは作品の大小は関係ないと思っています。だから「手を抜かない」ってことかなと思います。その結果、舞台に立って観客の皆さんの表情を観た時に“作って良かったな”と思えることが1つのゴールなのかなと思っています。

磯村:もちろん僕も芸能界でデビューする前は「有名になりたい、人気者になりたい」という思いはあったんですけど、やっぱりそれだけではこの世界では通用しないと思って、「俳優」というものをやりたいって考えた時に「芝居ができないとダメだ」と原点回帰しました。そこからは単純に売れてやるってことではなく、ちゃんと自分でお芝居に向き合って一つ一つの舞台を積み上げていきたいなという方向に意識が変わったんですね。
「有名になりたい、人気者になりたい」という気持ちはなくなって、向き合う作品一つ一つにどれだけ愛情を持って臨めるか、その時は苦しいかもしれないですが、その先に沢山の人に届くということがあれば良いなと思うようになりました。
――磯村さんと言えば、台本を深く読み込み自分の中に人物像を落とし込んだ上で、現場ではそれをリセットしてセリフだけが入っている状態で臨むという“内面的なアプローチ”と、役柄にビジュアルも近づけることを意識される“外見的なアプローチ”をされているかと思いますが、本作での役どころではそれぞれどんなことを意識されましたか?
磯村:外見については原作ものではないので、メイクさん、スタイリストさん、監督たちとイメージを擦り合わせて作っていきました。内面的には、ライブ配信者としての素人感や、ライブ配信で有名になりたいとただただ浅はかに思うちょっと危険な匂いもするキャラクターを演じられれば良いなと思います。

――藤井監督は “総監督”という普段とは違った立ち位置で本作に携わられたかと思いますが、何か意識されたことはありますか?
藤井:現場に「監督」と呼ばれる人は1人しかいらないと思っているので、それぞれの撮影現場には行かないようにしました。コンセプト決めや企画の打ち合わせはもちろんやりましたが、こちらの意見を押し付けたりはせず、それぞれの監督にSNSについて考えていること「SNSへのラブレター」を自由に表現してもらうようにしました。





































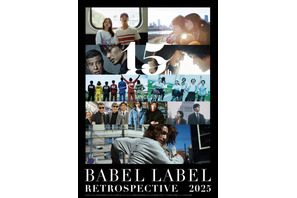


※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください