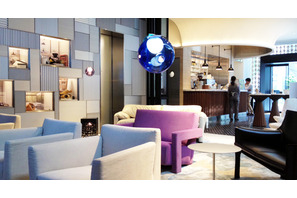プロポーズ大作戦×すてきな片想い?
――密かに恋心を抱く男性のプロポーズをサポートする主人公のほろ苦い失恋を描く「OPERATION BARN OWL」。共同脚本の落合賢との脚本づくりのプロセスは?
「落合さんにいただいた初稿の段階で『プロポーズをする』ということと『主人公の女性が恋をしている』という設定はあったんですが、もう少し違ったお話だったんです。より主人公の目線で物語を進めること。そしてプロポーズを面白く見せることを軸に手を加えていきました。主人公のエレンは親友のジョナのプロポーズを応援するけど、彼女は本心ではそんなことはしたくない。彼女が抱えている葛藤をうまく活かせないかと苦心しました。プロポーズの部分を面白く描こうとし過ぎると、エレンが消えちゃうんですね(苦笑)。そのバランスをどう保つかが難しいポイントでした。
日本の少女漫画的? 『切ない』を描く!
――プロポーズというポジティブでおめでたいイベントを扱いつつ、それで失恋する側の視点で描く。この“切なさ”を描くのは日本人監督ならではと言えるのでは? 大川監督自身、過去の作品でも、10代の頃から読んできた少女漫画に強く影響を受けていると語っているが…。
「今回、初めての恋愛映画で、特定の少女漫画に直接影響を受けたわけではないんですが、確かにすごく日本的な物語だなというのは撮り進めながらも感じていました。それは私が日本人だから自然とそうなったんですが、同じ脚本で欧米の監督が撮っていたら、あそこまでエレンの感情を追わないだろうと思います。英語でも“HAPPY SAD”という言い方はしますし、日本的な“切ない”という感じは分かってはもらえるんですが、言葉で説明しづらいですね。エレンの切なさの度合いも、やり過ぎると『もう分かったから!』となっちゃう(笑)。エレンが悲しんでいるけど、それを堪えているという見せ方をしたんですが、黙っている人を気にすることが出来るのはやはり、日本人的な感覚ですよね。実際、こちらで仕事していても、黙ってたらスルーされますからね(笑)。
結末の解釈は視聴者次第!?
――失恋というビタースイートな物語を描いているが、最後の最後でエレンが受けとるのは哀しみか? それとも希望なのか? はっきりとは示さない。
「答えを『これです!』とバンと出すのもひとつのやり方ですが、この作品ではそれは見る方に能動的に探して、考えてもらった方が楽しんでいただけると思います。アメリカから日本に帰ってくると日本のTVはすごくテロップでの説明が多いなと感じます。慣れるとグラフィックとしても面白いんですが、知ろうとする意識や、能動的に聞いて理解しようとする力が低下している気もしますね。またアメリカに戻ってドラマを見ると、疲れるんですが(笑)、そうやって知ろうとする努力が必要なのかなと。そういう意味で、作り手側がお客さんをグイと引っ張るような努力や工夫も必要なのかなという気がしています。
アメリカでの映画製作の刺激と苦労
――今回、レクサスおよびワインスタインカンパニーの後援を受けてこれまでと違う形で作品を作ってみて、刺激され、学んだ点も多かったよう。
「撮影は3日間で、これまで見たこともない機材などもあって(笑)、楽しかったです。印象的だったのが、現場であるカットを撮って、私がもういいと思っても『いろんな方向からのショットも抑えておけ』と何度もアドバイスされたこと。向こうは撮影後の編集の段階でのオプションをなるべく多く押さえておくのを大事にするんですね」。
――撮影だけでなく、その後の過程でもこれまでにない経験に触れ、発見があった。
「実際、先ほどの話の“切なさ”を描くという点で、今回、編集作業がかなり重要だったんですが、スピルバーグの助手を務めているプロの編集の女性がついてくれて、すごく楽しかったです。ただ、最後のエレンの表情のアップのカットは、私が最初に編集してからほとんど変えずにそのまま使ってるんです。メンター(※本企画で監督にアドバイスを送る5人の映画関係者。アントワン・フークア監督、女優のケイティ・ホームズらが名を連ねる)のフィリップ・ノイス監督にも『あれ、よくそのまま使ったね。勇敢だね』と褒めて(?)いただきました(笑)。今回、編集でリズムや起伏をつけて表現するというのを学ばせていただきました。全体を通じて、一番すごいなと思ったのは、ポッと出の日本人の女の子のビジョンを信じて『何がしたいのか?』と聞いて、こちらが伝えたことを実現するのに何が必要かを一緒に考えてくれるところ。そこでこちらも帰ってきた返事を噛み砕いて自分で答えを出さなくちゃいけなくて、そういう作業を通じて自分の中からもいろんな発想が出てくるということに気づかせてもらい、勉強になりました」。

乙女なドラマの着想は…?
――幼なじみの“プロポーズ大作戦”を応援するエレンだが、実は彼にずっと恋心を抱いていて…という非常に乙女チックな物語を最初に考え出したのは、映画監督としても活躍し、本作では脚本を担当した落合賢さん。
「意外と僕の中身は乙女なのかもしれません(笑)。アメリカ人はわりと公開プロポーズが好きで、YouTubeなどでよく映像が上がってるんです。壮大に歌ったり、踊ったり、ドッキリでやったら失敗したり(笑)、ユニークなんです。それを描きたいと思ったけど、男女がプロポーズしてくっついて、というのではありきたりだなと思い、そこから出てきたのが今回の物語。幼なじみのプロポーズを応援するけど、本当はしたくない。彼の恋人の『YES』という答えがエレンに対する『NO』になる――そこで大きな葛藤が描ける。僕のいままでの作品にない、ビタースイートなラブストーリーで大きな挑戦になるなと思いました」。
大川五月監督の演出への信頼!
――落合さんにとって、自身が手掛けた脚本を別の監督が映画化するというのは初めての経験。脚本づくりにおける共同作業からその後の過程はどのようなものだったのか?
「最初にお渡しした初稿に対し、大川さんがご自分のアイディアを加えて寄せていくという感じで、互いの良いところを詰め込みつつ、大川さんのビジョンで製作していただいてます。ただ、エレンという主人公のキャラクターをどう見せるか? という部分は最初にしっかりと話を詰めましたね。切なく、ビタースイートな物語を描く上で、観客にしっかりと彼女に共感・感情移入してもらわないと成り立たないので。例えば、彼女がウクレレを弾くシーンがありますが、じっくりと時間をかけて人物を知ってもらえる長編映画と違い、ああした短いシーンでキャラクターを理解してもらうというのはショートフィルムならではの描き方だと思います」
――実際に完成した作品を見ての感想は?
「自分が書いた脚本は我が子のような存在ですから、正直、最初は不安でしたが、僕は自分で監督もやるからこそ、監督を信じないといけないという感覚は自然と持っていました。大川監督の作品は心に響くものが多く丁寧にキャラクターを描いてくださる方なので、お任せしようと思いました。作品を見て、実際にキャラクターの描かれ方は脚本上にはなかった大川さんの演出の賜物だと思いましたし、もし僕が自分で映像化しても、こうはならなかっただろうなという新鮮な驚きがありました。大川さんが作り上げた世界が、良い意味で自分のイメージと違ったことで勉強になりましたね」。
アメリカで映画をつくるということ
――落合さんは現在、アメリカ在住だが、日本でも長編映画『タイガーマスク』を監督するなど、30代前半の若さで既に日米での映画製作に携わり、さらに長編・短編どちらの経験も持つ。本作はワインスタインカンパニー製作による、短編としてはかなり規模の大きな作品となったが、アメリカの老舗スタジオとの仕事はどのような経験、発見をもたらしたのだろうか?
「ワインスタインやレクサスという一流の存在と組むことで、作品の“重さ”について考えさせられる部分は多かったですね。思いつきで企画を通すのではなく、アイディアがあり、それを通すために多くの人を説得しないといけないんですが、その過程で企画が磨かれていくんですね。作品の規模が大きいということはリスクも大きくなること意味します。その製作の過程で高いハードルをクリアしながら作品を磨き上げていく作業は、これからもやっていかなくちゃいけない作業だと感じました。ひとりよがりでなく、ステップを踏んでいろんな方に意見もらい、説得する作業の重要性を実感しました」。